人材業界の現状課題と今後の動向について解説

近年の日本では、少子高齢化に伴う労働人口の減少や働き方改革による多様で柔軟な働き方の浸透、そして新型コロナウイルスなどさまざまな要因により、多くの企業が影響を受けました。それに伴う人材業界への影響も大きく、さまざまな課題に対応していくことが求められます。
とくに、直近数年におけるアフターコロナやDXへの対応、労働人口の減少といった中長期的な問題に対し、今後の対応に課題を抱えている人材業界の方は多いでしょう。
この記事では、人材業界を取り巻く環境や課題、そして今後の展望を解説します。
人材業界の主な事業
人材業界とは、採用に課題を持っている企業と仕事を求める求職者を結びつける業界のことです。人材業界には大きく6つの事業があり、それぞれ役割が異なります。
人材派遣
人材派遣は、派遣会社が人材を求める企業に派遣社員を派遣し、企業と求職者をマッチングさせるサービスです。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結ぶため、派遣先企業の指示のもとで業務を行いますが、給与の支払いや福利厚生などは派遣会社が行います。
また、株式会社矢野経済研究所が2022年に実施した調査によると、人材派遣業の市場規模は9兆2,000億円でした。前年度比で6.6%増加しており、人材派遣業の市場規模は年々増加傾向にあります。
市場規模拡大の理由として、政府による同一労働同一賃金制度により、派遣社員一人あたりの請求単価の上昇や雇用維持の動きが挙げられるでしょう。また、2021年度以降の経済活動の正常化に伴いサービス需要が高まっていることも、市場規模拡大の一因となっているのです。
出典:株式会社矢野経済研究所
人材紹介
人材紹介は、人材を求める企業に対し条件の合う求職者を紹介するサービスです。企業に人材を紹介したのち、無事に採用に至った場合は企業から紹介手数料を受け取ります。なお、人材紹介会社はあくまで企業に人材を紹介するだけであり、雇用契約については求職者と紹介先の企業が直接結ぶことになります。
矢野経済研究所の調査結果では、2021年度の人材紹介業の市場規模は2,960億円(前年同比17.5%増)でした。市場規模が拡大した理由として、コロナ禍の影響により2020年度は市場規模が縮小したものの、2021年度にかけて経済活動の正常化に伴う人材需要の高まりにより、市場規模が拡大したことが挙げられます。
再就職支援
再就職支援は、企業が事業規模の縮小などによりやむをえず人員削減を行う際、再就職支援会社が再就職を支援するサービスです。再就職支援会社は人員削減を行う企業と契約を結び、退職者の再就職先を保証するための委託費用を受け取ることで、代わりに退職者の再就職先を見つけます。
サービスとしては、以下のような内容が一般的です。
・退職者のカウンセリング
・自己分析のサポート
・求人の紹介や模擬面接
・履歴書や職務経歴書の添削
・人員削減を行う企業への助言
矢野経済研究所の調査結果によると、2021年度の再就職支援業の市場規模は321億円(前年同比5.2%増)でした。2021年にかけて、コロナ禍の影響により人員削減を行う企業が増えた影響で、再就職支援業の市場規模が拡大したのです。
しかしその後は経済活動の正常化に伴いサービスの需要が落ち着いてきたため、市場規模の成長は鈍化傾向にあります。
業務請負
業務請負とは、製造や物流といった企業における一部の業務を代行するサービスのことです。人材派遣と混同されますが、人材派遣が派遣先企業の指揮命令のもと業務を行うのに対し、業務請負は請負会社が指揮監督を担う点が大きな違いです。
業務請負を依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
・人材育成にかかるコストや手間を省ける
・指揮命令にかかるコストを削減できる
・労務管理などが不要になる
キャリア形成支援
キャリア形成支援は、キャリア相談やセミナー・研修などを提供するとともに、その後の就職支援まで一貫してサポートするキャリア形成支援サービスです。最近ではIT業界の需要の高まりもあり、「半年間のITプログラミング講座を受講しSEとして就職を目指す」といった、IT系専門スキルを習得できるものが人気を集めています。
料金体系は、セミナー・研修などを有料にし受講料金を受け取るものもありますが、多くが就職先の企業から紹介料を受け取る仕組みです。
求人広告媒体運営
求人広告媒体運営とは、企業の求人情報をwebサイトやフリーペーパーなどのメディアに掲載することで、求職者を集めるサービスをいいます。求人を出す企業に、募集人数や企業の強み、応募条件などの情報をヒアリングし、求職者に注目されるような広告を作成します。
また、人材コンサルタントとしてのサービスを提供するケースもあり、例えば企業の求人に関する課題から、求める人物像や求職者の注目を集める企画などを提案するのが特徴です。
料金体系は、メディアを通して求職者から応募があった場合に、掲載した求人企業から広告費として料金が支払われます。
人材業界が抱える短期的な課題
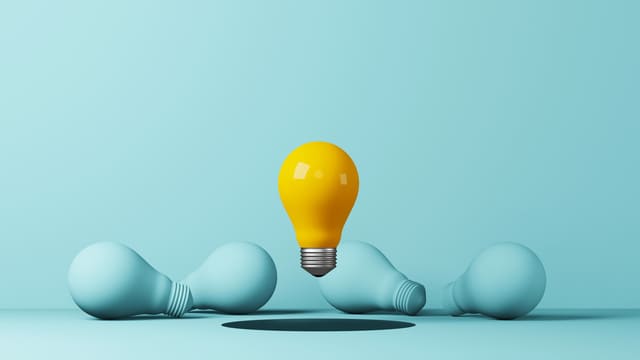
ここ数年で、人材業界を取り巻く環境は大きく変化しました。特に、コロナ後の有効求人倍率の回復や多様な働き方の浸透、IT・デジタル技術の発展は、今後の人材業界に大きな影響を及ぼすでしょう。
ここでは、人材業界の現在~今後数年間における状況と、主な課題を解説します。
有効求人倍率の回復と人手不足
コロナショックのあった2020年度の有効求人倍率は1.18倍でした。前年の2019年度と比較すると0.42ポイント低下しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響が色濃く出ています。しかしその後、有効求人倍率は徐々に回復し、2022年1月は1.20倍、2023年1月では1.35倍まで回復しています。
コロナ禍においては、ホテル・飲食・旅行関連・航空業界といったさまざまな業界で、採用活動を縮小または停止していました。しかし最近では、経済活動の正常化に伴い採用活動の再開も進み、数年でコロナ前の水準に戻る可能性があります。
一方、多くの企業で人手不足の状態に陥る恐れがあります。特に、建設業や運送業、医療・福祉分野はすでに人手不足の状態が続いており、今後ますます人材不足に悩まされるでしょう。人材業界は、こうした人手不足の状況に対応することが求められているのです。
アフターコロナの働き方への対応
新型コロナウイルスの感染拡大により、オフィスではなく自宅で働く「テレワーク」による働き方が浸透しました。テレワークは、就業場所や時間にとらわれない柔軟な働き方ができるため、今後も継続してテレワークを行う企業が増えることが予想されます。このような変革に対し、人材業界には下記のような対応が求められます。
・リモートへの対応
人材業界の働き方でも、リモートワークへの対応が必要です。例えば、求職者との面談をオンラインに切り替えることにより、求職者側も時間や場所に捉われず気軽に面談できるようになり、スカウトメールに対する返信率の向上が期待できます。
一方、オンラインによる弊害として「求職者に対しより丁寧なコミュニケーションが必要になった」という課題も生じています。今後の人材業界には、こうしたメリットや課題を踏まえて、リモートへ対応した体制づくりが求められるでしょう。
・転職者の増加への対応
多様な働き方の浸透により、転職者の増加が想定されます。しかし、仕事やライフスタイルに対する価値観の変化により、企業側と求職者側のニーズを両立させることが難しくなっているのが現状です。
企業側と求職者側の双方のニーズを調整し互いに満たすことで、就業を成立させる人材サービス業の需要が高まるでしょう。
DXへの対応
競争の激しいビジネス社会を生き残るために、DXによる組織改革やビジネスモデル変革への取り組みは、すべての業種において欠かせない時代となりました。多くの企業がDXに取り組み始めており、今後ますます推進されるでしょう。
人材業界においても例外ではなく、特にさまざまな業種に人材を派遣する人材派遣業のDX化は、多くの業種に影響を与える重要な取り組みといえます。
人材派遣業は以下の3つの特徴を持つため、デジタルによる課題解決に取り組みやすいと言われています。
・派遣先と派遣スタッフ、そして派遣会社の三者間における情報の共有や連携の必要性が非常に高い
・ペーパーレス化できる業務が多い
・勤怠管理や給与前払いなどが、デジタルによってリアルタイムに処理できる
デジタル化は、業務の効率化やコスト削減などにつながり競争力を高めるでしょう。
一方、まだDXに取り組めていない企業も多くあるのが現状です。こうした企業は、次第に競争に勝ち抜けなくなる恐れがあるため、人材業界においても今後DXへの対応は不可欠なのです。
人材業界が抱える中長期的な課題とは?
今後日本においては、少子高齢化が進むことが見込まれます。それに伴う労働人口の減少や働き方の変化などは、人材業界にとって大きな課題となるでしょう。
ここでは、人材業界が抱える中長期的な課題を解説します。
労働力人口の減少
少子高齢化の影響により、将来の労働人口は減少するでしょう。総務省が発行している「情報通信白書(平成28年版)」によると、2030年には日本の総人口は1億1,662万人まで減少すると見込まれています。また、生産年齢人口(労働力の中核をなす15〜64歳の人口層)は、2030年には6,773万人(2020年は7,341万人)まで減少すると予測されています。14歳以下の人口については、1982年から連続で減少が続いており、少子化に歯止めがかかっていないのが現状です。
多くの企業では、職場への適応力や将来性から「若年層」の採用を希望する傾向にあります。しかし、若い労働力は今後減少すると考えられるため、企業が若い労働力を確保するのが難しくなる可能性が高いのです。
そのため、人材業界は若い労働力の活用だけでなく、中高年層のスキルや経験を適切に評価し、企業と求職者をマッチングさせ雇用につなげる必要があります。他にも、外国人労働者の確保やAIによる業務の自動化により、若手の労働力を補う工夫を求められることもあるでしょう。
出典:情報通信白書
働き方や雇用形態の変化
テレワークの普及や働き方改革の推進などにより、「柔軟な働き方」や「雇用形態の多様化」が注目されるようになりました。こうした働き方や雇用形態の変化は、今後中長期的に見ても加速していくでしょう。多様な働き方や雇用形態の多様化は、具体的に以下のようなものが挙げられます。
・テレワーク
・フレックスタイム制
・時差出勤制度
・短時間勤務
・短時間正社員
・副業や兼業
・ジョブ型雇用
・業務委託
求職者側のニーズとしては「テレワーク」や「フレックスタイム制度」など多様な働き方を求められることが増え、一方で企業側のニーズとしては、終身雇用制度の廃止に伴う「ジョブ型雇用」や「業務委託」が注目されています。
今後人材業界は、こうした求職者と企業側のさまざまなニーズをしっかりと把握した上でマッチングさせ、雇用に結びつけることが重要です。
高齢者の就労への対応
日本では、今後さらに少子高齢化が進み若年層の労働人口は減少していきますが、一方で高齢者層では老後資金の不足から、定年後も就労による収入を得たいというニーズが高まることが想定されます。そのため企業には、高年齢労働者の活用を検討する必要があるでしょう。こうした背景から、人材業界は高年齢労働者が働きやすい労働環境の整備も課題となっています。
AIの台頭と専門スキルへの需要拡大
近年の目覚ましいIT技術の発展により、さまざまな仕事がAIに代替されるようになりました。例えば、事務職のデータ入力などの単純作業はIT技術により省略化され、人材の需要は減少していくことが予想されます。そのため、今後はAIでは代替できないような専門的な職種への需要が高まるでしょう。
こうした背景から、派遣会社は自社社員の教育に注力し、IT分野などの専門性の高い人材を育てていくことも重要です。
人材業界の今後の展望は?

結論からいうと、今後人材業界のニーズは高まり、市場規模の拡大が期待できます。その理由として、以下の2点が挙げられます。
(1)労働力不足による人材需要の高まり
パーソル総合研究所によると、2030年の労働需要は7,073万人であるのに対し、労働供給は6,429万しか見込めず、約650万人もの労働力が不足すると予測されています。
また、現在政府が推進している「女性」「高齢者」「外国人雇用」の働き手だけでは労働力を補いきれないと分析しており、これから人材への需要はますます高まるとされています。
前述のように、労働人口の減少により人材のマッチングは難しくなっていく可能性があるものの、企業側の人材需要は高まることから、人材業界全体の売上は増加していくことが期待されます。
出典:パーソル総合研究所
(2)雇用形態や働き方の変化
終身雇用制度の廃止や副業などの浸透により、個人を重視した働き方が主体となるでしょう。終身雇用制度の廃止により、転職などによる雇用の流動化が進み、求職者側からも企業側からも人材サービスのニーズが高まります。
また、ワークバランスを重視した働き方のニーズにより、以前とは異なる新たな人材サービスの需要が生まれることも期待できます。
人材派遣企業が取り組むべきこと
今後の労働力の減少やIT技術の発展、働き方の多様化などに伴い、人材派遣企業は現状のままでは生き残れない可能性があります。ここでは、人材派遣企業が今後取り組むべきことを3点解説します。
優秀な人材の確保や育成
今後の労働人口の減少を補うためには、優秀な人材の確保や人材育成によって労働者一人一人の生産性を高める必要があります。また、待遇や福利厚生を充実させるとともに研修制度やサポート体制を整えることが重要です。
他にも、求職者を獲得するためのルートを開発しておくことも必要となるでしょう。主婦や高齢者層に加え、場合によっては海外からの人材も検討の余地があります。
事業の多角化や付加価値の創出
今後も、人材派遣会社の競争は激しくなることが予想されます。その中で競争に勝ち残っていくためには、事業の多角化や付加価値の創出が不可欠となるでしょう。
その際、人材紹介業への参入は一つの方法です。人材派遣業界は景気の影響を受けやすく、景気が悪くなると派遣先企業が人材関連の予算を縮小したり、雇止めをしたりすることが多くなるため利益を上げづらくなります。一方、人材紹介業は人材派遣業に比べて、営業や派遣社員へのサポートなど人材管理にかかるコストがあまりかからないため、利益率が高くなる傾向があります。人材派遣業は既にあるノウハウを生かしながら、人材紹介といった他の事業を展開することで、営業利益率の改善を目指せるのです。
また、多くの人材派遣企業がある中で、求職者や企業はよりサービスの優れた企業を選ぼうとするでしょう。そこで人材派遣企業では、派遣社員に対する手厚いサポートや多様な仕事の紹介や、企業側に対するスピーディーで優秀な人材の紹介など、他社にはない強みや付加価値のあるサービス提供が求められます。
その他にも、事業の利益率を改善するための試みもおすすめです。人材派遣会社では紹介料のうち、70%が派遣社員の給与にあてられ、残りの大部分を人材の教育や、社会保険料の支払い等にあてるため、ほとんどの場合、営業利益率が一桁台ということも少なくありません。
業務の見直しによって、利益率を改善し、自社の経営を見直してみると良いでしょう。
DXによる効率化・スピードアップ
DXによる業務の効率化やスピードアップも取り組みにおいて必要となるでしょう。
人材業界は市場が目まぐるしく変化し、ニーズも時代に合わせて多様化しています。そのため求職者側も企業側もスピーディーでニーズにあった情報提供を求めています。
そこで人材派遣企業は、ITツールの導入など、DXを進めデータを一元管理することで、タイムリーな対応を可能にする必要があるのです。
スピーディーでニーズにあった人材を企業に紹介できれば、求職者にとっても求める仕事が見つけやすくなり、人材派遣会社のスタッフも、業務の効率化により働きやすくなるメリットがあります。
まとめ
近年の急激な社会情勢や雇用情勢の変化により、人材業界は大きな変化が求められるようになりました。今後の労働人口の減少や働き方の変化、IT技術の発展などの課題に適切に対応しなければ、人材業界で勝ち残ることは難しくなるでしょう。
このピンチを逆手にとって、人材業界の今後を見据えた対策をとることで、課題を解決でき、業績を大きくさせるヒントを得られるかもしれません。
「STAFF EXPRESS(スタッフエクスプレス)」では、人材業界の業務を効率化することができるシステムをご用意しています。
業務の効率化を課題に感じている担当者の方は、ぜひそちらも合わせてご覧ください。














